
前回のコラムでは、教室内における学びを紹介した。今回のコラムでは、教室外における学びについて紹介する。
留学を通して、私の中国語が伸びた、あるいはその成長を実感したのは教室外がほとんどであった。私は2人1室の寮で生活しており、一緒に寮生活をしていた中国人ルームメイトをはじめ、クラスメイト、寮の舎監、タクシーの運転手などとの会話を通してよりリアルな中国語を身に付けようと努力した。わざわざ話すような場面でなくても、何かを言うことに意味を見出し、かれらとコミュニケーションを取ろうとした。何もしなくても中国語のインプットが多いことから、どれほどアウトプットができるかに重点を置いていたのかもしれない。中国人ルームメイトは、最も身近にいる中国語母語話者であり、私は彼女に私の中国語に間違いがあれば随時教えてほしいと言っていた。映画を見に行ったり、料理を作ったり、カラオケに行ったりととても充実していた。映画を見終わったら、内容や感想を言い合うこと、料理の作り方を説明しながら味について述べ合うこと、教えてもらった中国語の歌を歌ってみることなど、とても些細なことのようだが、このような積み重ねが中国語の成長につながったと考える。
また、中国人ルームメイトの他に、私には2人のランゲージパートナーがいた。かれらは日本語や日本の文化に興味があり、私たちは互いの母語や文化について教え合った。カフェでのお喋りや、博物館、美術館などに出かけ、自然な中国語を身に付けたといえる。かれらとの交流を通して、中国の食文化やコミュニケーションの在り方についても自然と学ぶことができた。ルームメイトと異なり、ランゲージパートナーは日本語が話せたことから、理解ができない時は、日本語での説明をお願いすることもあった。
この他に、教室外での学びとして私が実践していたことは、今後使えそうだと思った表現を携帯にメモしていたことである。中国語母語話者との会話や、ドラマの中で使われている表現で、今後使ってみたいと思う表現は、どのようなシチュエーションだったのかも補足で書き添えながら、メモを取っていた。また、毎日実践することはできなかったが、楽しいことがあった日や、旅行に出かけた日は中国語で日記を付けていた。その日感じたことを自分の字で書き記しておくことは、何気ない毎日を過ごす上で非常に重要であり、現在もその日記を通して過去を振り返ることができる。
中国人ルームメイトやランゲージパートナーの支えがあったとはいえ、中国での生活が全て順調で、言語に関する困難がなかった訳ではない。かれらは私が日本から来た留学生であることを知っている。しかし、寮の外へ出ると、周りの人々は私がどこから来たかは外見上では判断できない。タクシーの運転手と会話することがよくあったのだが、私はかれらが話す中国語が理解できないこともあった。かれらが話す中国語はリスニング教材で流れるような分かりやすい発音ではなく、とても早く、方言が混じっていることもあったからだ。そのような時は、「もう一度ゆっくり言ってもらえますか?」といい、理解しようと努力した。ただ、独り言のように政治や経済のことを話す運転手も少なくなく、全てを理解することは諦めて、うんうんと聞いていたこともある。「分からない」ことを全て知ろうとすることは難しいが、だからといい、耳を閉ざすのではなく、「分からない」ことを客観視しながら、言語能力向上のために何ができるのかを探していく必要があると感じた。
留学先でのあらゆる活動が言語習得と密接に関係していたといえる。スーパーで食材を買う時、宅配ピザを受け取る時、寮の部屋の電気が切れて事務局に問い合わせる時など、すべての活動が中国語習得につながっていた。これらの活動は、言語習得という面以外でも、私を大きく成長させたといえる。次回のコラムでは、留学を通して私自身にどのような変化・成長があったのか、言語以外の面から考えてみることにする。

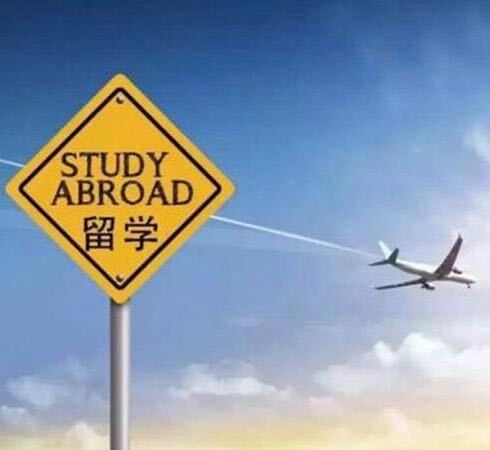

.jpeg)
.jpg)
.jpg)