.jpg)
TAさんによる言語学習についてのコラムの第13弾を追加しました。言語文化研究科D2の張碩さんによる、夏休みの終わりの、日本語との出会いです。
.jpg)
TAさんによる言語学習についてのコラムの第13弾を追加しました。言語文化研究科D2の張碩さんによる、夏休みの終わりの、日本語との出会いです。
.jpg)
「なぜ日本に留学されたのですか」という質問は日本に来てから何度も何度も聞かれました。私はいつも「中学生の頃、日本のドラマを初めて見ました。その時から、日本で生活してみたいなぁと思いました」と正直に答えていました。
15歳の夏休みの終わりに、家でごろごろしていた私は偶然にテレビで放送された日本ドラマ「1リットルの涙」を見ました。この悲しい物語に心を揺れ動かされ、涙が止まらなくなってしまいました。もし日本語が話せたら、このドラマについての理解がより深くなると感じました。そのような熱意を持って、日本語の五十音図から日本語を独習し始めました。
高校に入ってから、学業が忙しくなったため、日本語の学習も五十音レベルにとどまりましたが、休みの日に、中国語の字幕がついた日本のドラマを観るのは一番楽しいことになりました。その時、中国の字幕を付けなければ劇中の会話は聞いてもほとんど理解できなかったのですが、私は疲れを感じることなく、手帳のようなノートに好きな歌詞や台詞をたくさん書いて暗記しました。例えば、一番好きな日本ドラマ「ロングバケーション」での、主人公瀬名のセリフ「何をやってもうまくいかないときは、神様がくれた長い休暇だと思って、無理に走らない、焦らない、頑張らない、自然に身を委ねる」はどんな時に聞いても、癒し効果があると思いました。日本ドラマをはじめ、日本語の曲も、日本の小説も、日本語は私の友達のように、忙しく充実した日々でずっとそばにありました。
瞬く間に時間が過ぎ、高校3年の努力が実って、私は近所の大学に入りました。ずっとジャーナリストに憧れていたため、ジャーナリズム学科を選びました。受験競争が激しい高校と違い、自由度が高い大学では、専門知識を学ぶ以外に、日本語を勉強する時間もたっぷりありました。その時から、私は毎晩日本のドラマを観たり、歌を聞いたりして、日本に留学したい、日本で生活してみたい、ドラマの主人公が住んでいる場所を見に行きたい、昭和風の喫茶店でコーヒーを飲みたいというような思いが日々に強くなりました。留学の資格を取るため、私はN2(日本語能力試験2級)にチャレンジしました。残念ながら合格点には6点足りず不合格でした。気分が落ち込んでいましたが、冷静に振り返ると、その時の私は、日本語が好きなのに、真剣に本格的に日本語を学んだことが全くなかったことに気がつきました。自分の過ちを反省した上で、一年後の試験の合格を目標とし、一連の学習計画を作りました。まず、オンラインレッスンを受け、日本語の語彙、文法の勉強を続けました。次に、常に日本語のニュースを読んで、日本語の読解力を高めるとともに、日本文化や日本の物事に関する知見も蓄積していきました。さらに、生きた日本語を学ぶために、日本語のドラマを観る以外、週1回、日本語学科の日本人の先生の授業を聴講して、生の日本語に慣れるように努力しました。それをきっかけに、日本語学科の友達ができて、日本語に関する質問をよく解説してもらいました。それらの地道な努力や友達の助けによって、一年後の試験でN2に、やっと合格できました。ただし、日本語にずっと趣味や情熱を持っていましたから、深夜まで日本語の単語や文法を暗記することや、一つのニュースを何十回も聞いたことなど、私にとって辛い記憶とは言えません。
卒業してすぐ日本へ留学して、今は日本に来てもう7年になりましたが、日本ドラマ、小説や音楽に対してずっと消えない情熱を持っています。そして、幸運にも、その時にできた友達もずっと日本にいて、食事に出掛けるとか、バンドのコンサートに行くとか、日本語のように、ずっとそばにいます。
15歳の時の外出したくない、寝たくないと思い日本ドラマを一気に見ていた夏休みを一生忘れないと思います。
(張碩)
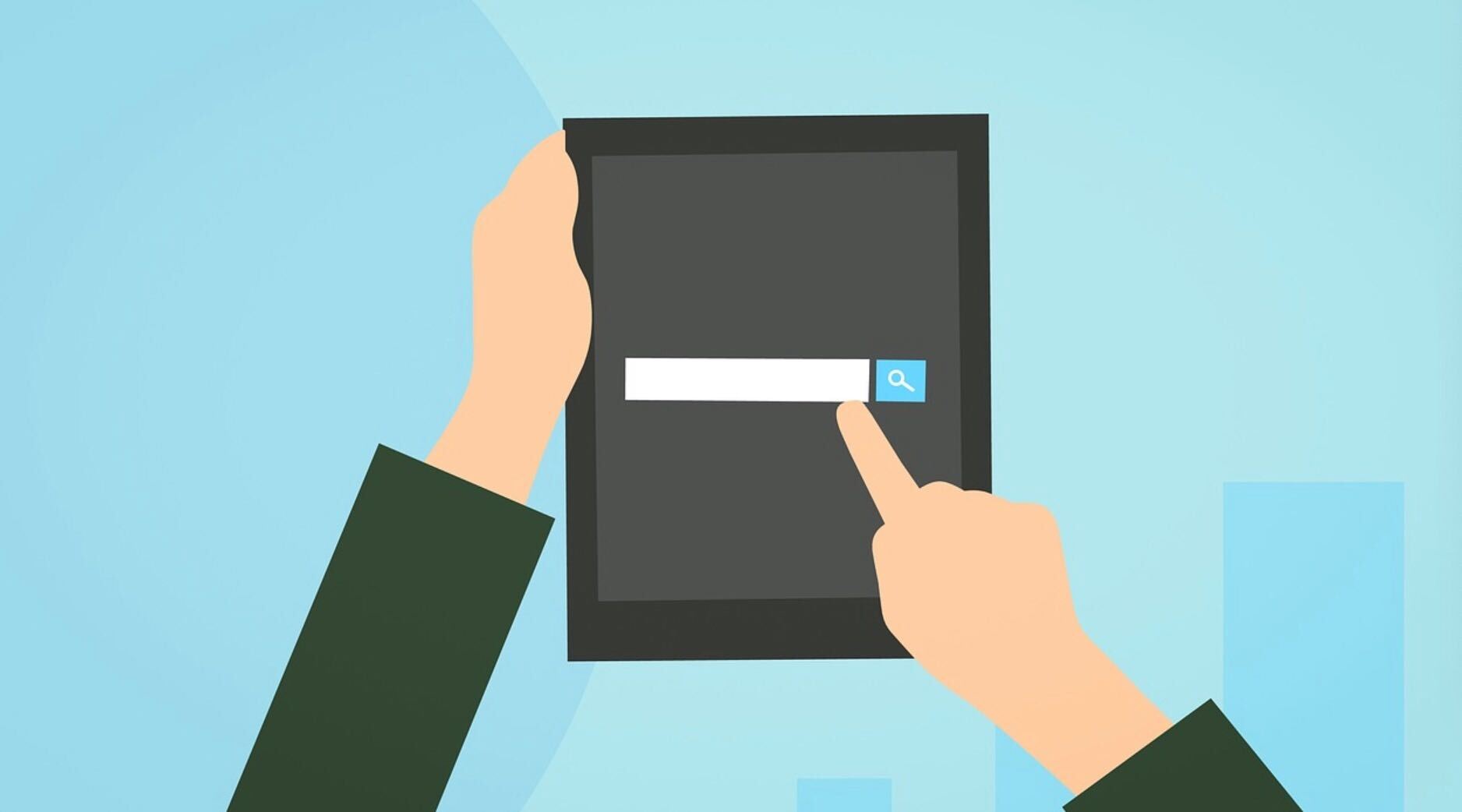
TAさんによる言語学習についてのコラムの第12弾を追加しました。言語文化研究科M2の蘇暁笛さんによる、「中国語・中国事情サイト4選」です。
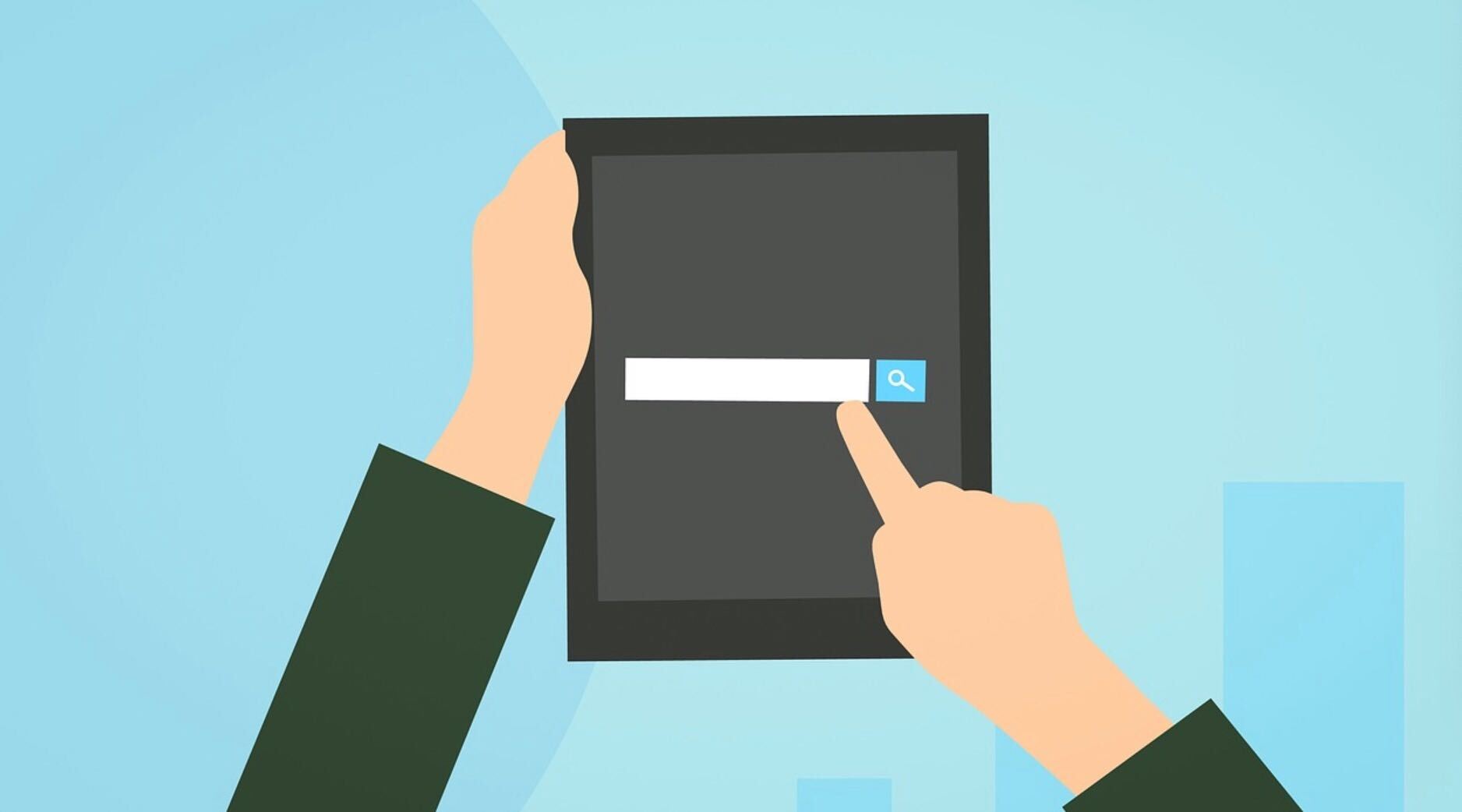
今回は中国事情・中国語に関する4つのサイトをご紹介していきたいと思います。
中国語を勉強している人、中国事情に関心を持っている人、日本語で今の中国を他人に説明する能力をアップさせたい人、ぜひ参考にしてください。
1、『人民中国』
大学時代、日本語学習に使われていた日本語雑誌『人民中国』をご紹介します。
『人民中国』は、1953年に創刊された中国唯一の日本総合月刊誌です。出版元は当時の外文出版社(中華人民共和国国務院直属)です。今は北京と東京にオフィスがあります。名前からのイメージで、政府系の紙媒体でかなり堅い内容ばっかりなのではないかと思っていたのですが、実際に読んでみると、すぐハマりました。
『人民中国』の創刊当時は世界的にイデオロギーの対立があり、記事の内容はほとんど中国の文化人や政治家からの寄稿が中心でした。60年代に入った頃から、日本人の寄稿が増えてきました。2001年から新しい理念のもとで大きくリニューアルしたようで、今は中国の政治経済、社会民生、文化観光、中日交流4つのコラムがあります。コラムの名前からはすこし堅いイメージがあるかもしれませんが、以下のように、最近のいつくかの文章のタイトルを見たら、全体の雰囲気がすぐわかると思います。
【政治経済】「中日感染対策は同工異曲 経済復興も足並みをそろえて」
「中日関係は新たな段階へ 両国首脳の大阪会談きっかけ」
【社会民生】「始まった!北京のごみ分別」
「私たちの対コロナ戦−−−配達員の一日」
【文化観光】「素晴らしい生活を送ることのできる都市トップ10」
「複雑な人間性を描くサスペンスドラマ「隠れた隅」、この夏ネット上で大
ヒット!」
【中日交流】「愛知から武漢へ 命のリレー」
「東京五輪聖火リレーのリハーサル 石原さとみさんも参加」
『人民中国』は今存続している唯一の日本語の紙媒体で、日本と中国のどちらでも販売されています。また、紙版・電子版以外に、現在はウェブ版もあり、より情報にアクセスしやすくなりました!
サイトはこちらです↓ぜひ、読んでみてください。
http://www.peoplechina.com.cn/
2、和之夢
和之夢には「以梦为马未来可期」、「可以帮你化妆吗」、「东游食物记」、「速食物语」、「和饭情报局」、「我住在这的理由」六つの番組があります。その中、最初の二つは完全な中国語番組で、後ろの四つの番組が日中関係の番組です。私は「我住在这的理由」というドキュメンタリー紀行番組をきっかけに和之夢を知ったのです。「我住在这的理由」は中国に住む日本人、また日本に住む中国人に密着し、異国で頑張っている彼らの姿を等身大に描く台本なしのドキュメンタリです。現時点で242回もの作品が出来上がっています。出演者は一般人だけではなく、乃木坂46の斎藤飛鳥、片寄涼太のような日本の芸能人もいます。「我住在这的理由」の一番魅力的なところといえば、やはり、個人の物語に焦点を当てるところではないかと思っています。
この番組の監督-−−竹内亮さんは非常に面白い方です。竹内亮さんは千葉県出身の日本人で、中国人と結婚し、今中国江蘇省南京市に住んでいます。竹内亮さんの話によりますと、「我住在这的理由」のような中国人向けの日本を紹介する番組を作ることを決意したきっかけは2010年のNHKの「長江 天と地の大紀行」という番組だったそうです。撮影の際、地元の人から「山口百恵は元気か、高倉健は今何してる?」と聞かれたことで、中国人に今の日本が知られていないことに衝撃を受けました。竹内亮さんは現在の日本文化や日本人のあり方を中国人に伝える、また、現在の中国文化や中国人のあり方を日本人に伝える素晴らしい仕事をしていると思っています。
和之夢のほとんどの動画は中国語・日本語の字幕両方ついていますので、中国語を勉強している方、日本語を勉強している方にぜひ利用していただきたいです。
公式ウェブサイトはこちらです!↓ぜひ利用してみてください。
https://www.hezhimeng.cn/pc/column/index
3、YouTuber:李姉妹ch
日本在住の可愛い中国人姉妹が開設しているYouTubeチャンネルです。登録者数は21.1万人ほどであり、中国語学習者の間で大人気のチャンネルと言えます。
姉妹二人とも今は日本に暮らしていますが、姉は中国生まれ、その後中国、日本、ニュージランドで生活していました。妹は日本生まれで、幼少期は中国で過ごし、6歳から日本在住になったそうです。家族の間に、日本語と中国語がミックスした「把タバコ放在桌子うえ」、「もう走了」、「你食べ終わって过一会再刷牙」のような「日中ミックス語」が当たり前のように飛んくる話が一番印象深いでした。実家は三重県そうで、三重弁も時々出てきます。
チャンネルでは、中国語や中国文化についての雑談動画や旅の動画などがアップされています。動画は二人自らの実体験に基づいた内容で、実用性が高くて、二人のやりとりも非常に面白いです。
リンクはこちらです!↓
https://www.youtube.com/channel/UCDhjThxt99rkGcjcEreyOQg/about
4、相原茂の中国語閑談
ネイティブなのに、外国人に聞かれた質問に答えられないといった経験は皆さんもあったと思います。大阪大学入学当初、授業で中国語の場合はどうなるかなどの質問がよくされました。その時、これは言える、それは言えないくらいだけで、うまく説明できない状態でした。自分の母語をよりよく知るために、当時ハマっていたApple Podcastで調べたところ、【相原茂の中国語閑談】という番組に出会いました。
相原茂先生は中国語コミュニケーション能力判定テスト(TECC)を実施している中国語コミュニケーション協会の代表であり、NHKのラジオ・テレビの中国語講座にも講師として10年以上出演しました。【相原茂の中国語閑談】は相原茂先生と中国語ネーティブの二人が届けるおしゃべり番組です。番組では、中国語言語表現だけではなく、中国の歴史、大学入試やインターネット文化などの日中異文化も色々紹介しています。勉強モードに疲れてしまった時、ご飯を作ったり、部屋を掃除したっりしながら、聴くのがオススメです。
実は、Apple Podcastで検索していただくと、中国語関連の番組は他にもたくさんあります。ぜひ検索してみてください。
【相原茂の中国語閑談】番組はポットキャストの方でもこちらのホームページでもアクセスできます。↓
http://aiharamao.seesaa.net/
中国語中国事情を知るには、他にもたくさんのサイトはあると思いますが、今回はお薦めする4つのサイトをご紹介しました。興味のあるサイトを選んで、楽しく中国語を勉強しましょう。
(蘇暁笛)

TAさんによる言語学習についてのコラムの第11弾を追加しました。言語文化研究科D1の太田真実さんによる、タイ語との出会い (インタビュー)です。

今回は、大学でタイ語を専攻した朴苑善さん(言語文化研究科、言語社会専攻、博士前期課程2年)にタイ語学習についてインタビューを行いました。
Q:初めてタイ語を勉強した時のことを教えてください。
A:タイ語を勉強するようになったのは大学1年生の頃です。私はタイ語を専攻していました。授業で初めてタイ文字を見たときは、とてもびっくりしましたね。「記号」、「絵」のように感じられたからです。とてもふにゃふにゃしていて、どの文字もなんとなく似たような印象を受けました。果たして私がこの記号のようなものを理解できるのだろうかとも思いました。タイ語の発音に関しては、とても柔らかく、可愛い印象を持ちました。
Q:タイ語はどのような言語なのでしょうか?
A:まず、タイ文字が存在します。日本語と同様に、母音と子音がありますが、それらの数は圧倒的に多いです。また、特徴として、母音を表す符合を子音の左右上下に付けます。左右上下のどの位置に付けるのかは、母音によって異なります。例えば、「◌ะ(a)」は、子音の右に、「 ิ(i)」は、子音の上に付けます。また、タイ語には5つの声調があります。ただ、同じ声調記号を用いても、子音の種類によって声調記号が表す声調と実際の声調が異なることがあり、とてもややこしいです。はじめはとても混乱していました。
Q:どのように勉強されていましたか?
A:基本的には授業で勉強したものを家で復習していました。まずタイ文字を暗記し、単語もたくさん覚えました。初めてタイ文字を見た時は、似たように感じられたものも自然と区別できるようになっていったのを覚えています。タイ語の電子辞書がないことから、紙の辞書にはすごく頼っていましたね。さらに、パソコンでタイ語が打てるようにタイ語専用のキーボードも購入しました。また、箕面キャンパスにはタイ人の留学生がたくさんいたので、かれらにタイ語を教えてもらっていました。タイ人の留学生は日本語がとても流暢で、タイでは日本語を学ぶ人がとても多いことも知りました。かれらと交流する中で、私もかれらが話す日本語みたいにタイ語を習得したいと思うようになりました。
Q:タイ語を勉強する中で、最も難しい/簡単だと考える部分は何ですか?
A:難しいと考える部分は、やはり文字だと思います。区別できるようになったとはいえ、今でも混乱することがあります。また、文章を読んでいる時、タイ語は分かち書きがないので、どこで区切れているのかよく分からない時が多々あります。日本語の場合、漢字と併用されていることから、単語と単語の切れ目がはっきりとわかるのですが、タイ語は分かりにくいです。これを克服するためには、まずは彙力を増やすことしかないと考え、単語をたくさん暗記しました。また、文章を読むときは、接続詞を一生懸命探しています。反対に、簡単だと感じる部分は文法です。活用表現がないことから、この部分は楽です。
Q:タイ語の魅力を教えてください。
A:タイ語を勉強していると、タイ語とタイの文化や国民性とが結びついていることを感じる時があります。大学3年生の時に、タイ(チェンマイ)に留学した経験があります。その時、「ไม่เป็นไร(マイペンライ)」という言葉をたくさん聞きました。この言葉は、「大丈夫」を意味しています。私が考えるに、タイの国民性として、のんびりとした性格の人々が多い印象があります。物事をポジティブに捉え、マイペースに生活することからも、この言葉をよく耳にした気がします。個人的にはとても素敵な文化だと感じています。また、国民性とは関係ないのですが、タイ語の挨拶「สวัสดี ครับ/ค่ะ(サワディクラップ/カー)」は、「こんにちは」でもあり、「さようなら」も意味します。会った時も別れ際も同じ言葉を使うことが初めは不思議な感覚でしたが、今となってはとても好きな言葉となりました。
Q:タイ語を勉強されている人々へ何かアドバイスはありますか?
A:新しい言語を勉強することは、新しい文化や人々に出会える場でもあると考えます。そのような意味で、勉強した言語を実際に使える場に足を運び、実践してみることがとても重要だと感じています。機会があるのであれば、学んだ言語を旅行や留学で使ってみるのも良いと思います。タイ語に関しては、始めは文字がややこしいので、混乱するかもしれませんが、慣れたら意外とできるものだと感じるようになります。私もまだまだ不十分なので、これからも頑張って勉強していきたいです。
タイ語に少しでも興味を持たれた方、タイ語を勉強してみてはいかがでしょうか。高度外国語教育独習コンテンツでは、基礎から発展まできちんと学ぶことができます。
http://el.minoh.osaka-u.ac.jp/flc/tha/index.html

TAさんによる言語学習についてのコラムの第10弾を追加しました。言語文化研究科D1の太田真実さんによる、「中国語と私」の中国語版、「中文和我」です。

我第一次接触中文是在小学二年级的时候。父亲热衷于教育,受他的影响我开始跟一个中国留学生学习中文。那时候,我也曾怀疑自己连汉字都写不好,为什么我要学中文。当时,我学会了拼音(中文发音表记法),背诵了日常生活中使用的单词。“你好”之后记住的单词就是“冰淇淋”,那时候比起背诵基础单词,我更想记住自己想知道的中文单词。背诵的时候,我喜欢做原创单词本,一边按类别整理一边学习。此外,我背过唐诗,也记过童谣,可以说从小就在快乐地学习新语言。
真正开始学习中文是在大学的时候。在那之前我所有的中文学习都像是“娱乐”性质的,所以我选择进入大学中文专业,想好好学习中文语法,以便掌握在社会上也能使用的中文。中文的语法和日语相比,给人一种比较简单的印象。其中我认为中文没有“活用表现”就是最大的原因。在表示否定的时候,把“不”、“没”这个词放在动词或形容词前面就好了,在表示过去的时候,基本上把“了”这个词加在句末,就可以表示它们的意思了。和存在各种动词活用的日语相比,我觉得中文语法是可以简单掌握的。
大学的课程主要是学习“阅读,写作”,“听力,口语”主要靠自己在课外多加练习。首先,关于“听力”部分,我是一边看中国电视剧和电影一边学习的。因为电视剧和电影中播放的中文速度太快了,所以我会反复按停止和播放按钮去看。还有,我会通过中文字幕,一边追着字幕一边理解。如果有喜欢的表达或者不明白的表达的话,就随时把它们写下来。我最喜欢看的电视剧是台湾翻拍的日剧《流星花园》。因为我已经看过日本版了,知道了内容,所以可以更加集中精力关注他们的对话。另外,在电视剧上还可以学习课堂上不怎么能接触到的年轻人的日常表达,这种学习方法也可以提高学习中文的动力。并且,在台湾使用的中文跟大陆的普通话的发音稍微不同,也有助于我理解中文的多样性。
在“口语”部分,我积极地和会说中文的朋友用中文交流。另外,为了掌握地道的中文,我还努力去理解在课堂上和电视剧中学到的单词在实际场合的用法。我说的虽然不是完美的中文,有时候会感到害羞,但我觉得不用太在意这些事情,要尽量用中文和朋友聊天。
第一次接触中文的是小学的时候,从那时开始学拼音,我几乎没有觉得发音特别难。但是,我也遇到了各样的困难,比如,日语的汉字有时和中文的汉字意思不同,它们会让我混乱。例如,中文汉字的“走”是“走路”的意思,而日语中的汉字“走”确是“跑步”的意思。如果是日语母语话者的话,看到中文的“走“,就容易联想到”奔跑“。另外,日语中的“歩”跟中文的“步”在写法上也稍有不同。不管哪种语言,在学习新语言时,母语自然会产生干涉。
我在学习中文的时候,一边品味上述的微妙的差异一边学习到了知识。对于两种语言中不可思议的差异性,以及为什么会产生这种差异性,我并没有消极地对待,而是积极地接纳了。另外,通过中文和大家产生联系的时候,我感到十分幸福,学习的动力也提高了。注意到中文和母语的不同,快乐地学习,以及通过语言学习和他人产生联系,是我在学习中文时最重视的事情。
(太田真実)
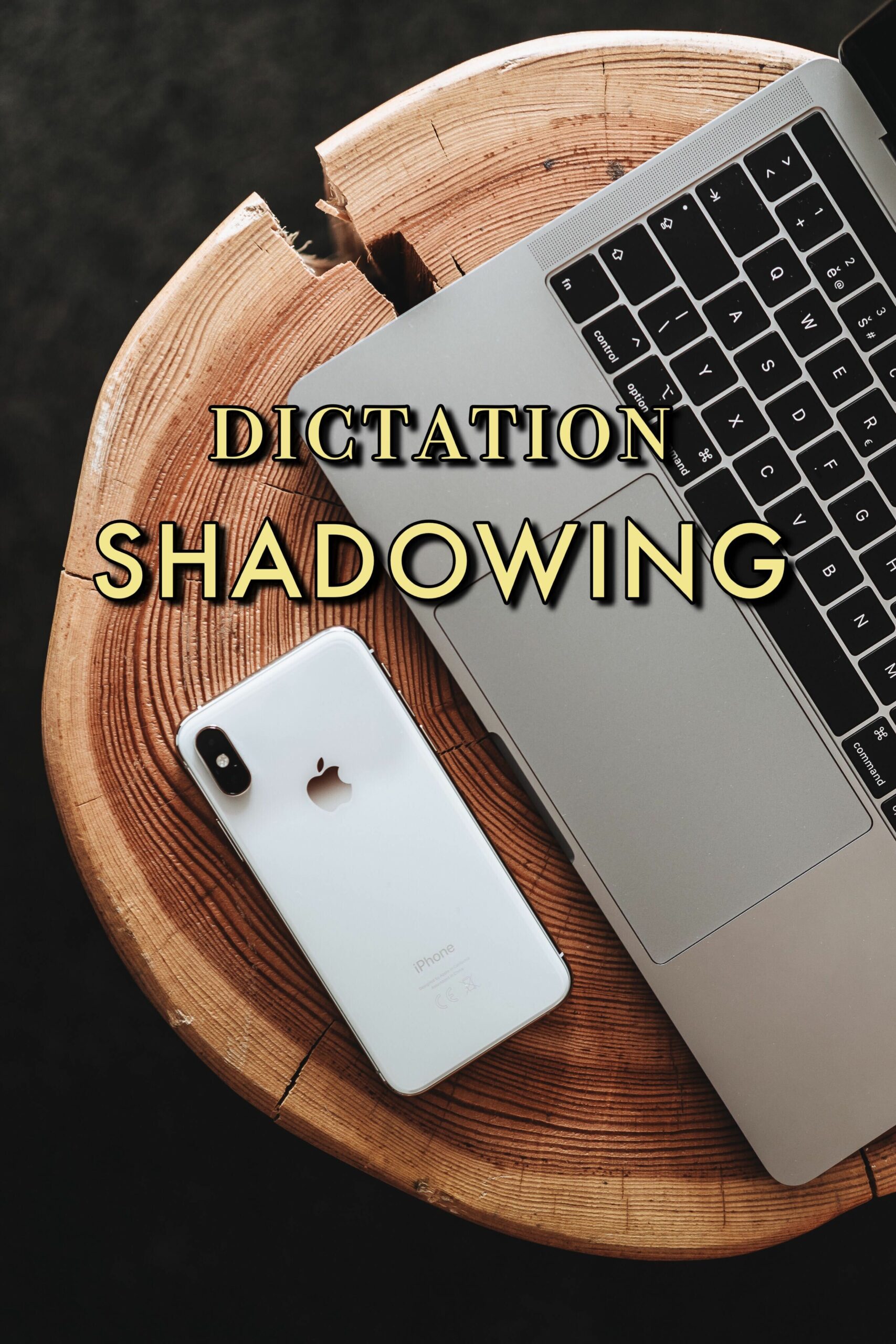
TAさんによる言語学習についてのコラムの第9弾を追加しました。言語文化研究科M2の蘇暁笛さんによる、ディクテーションとシャドーイングを組み合わせた効率的な言語学習です。
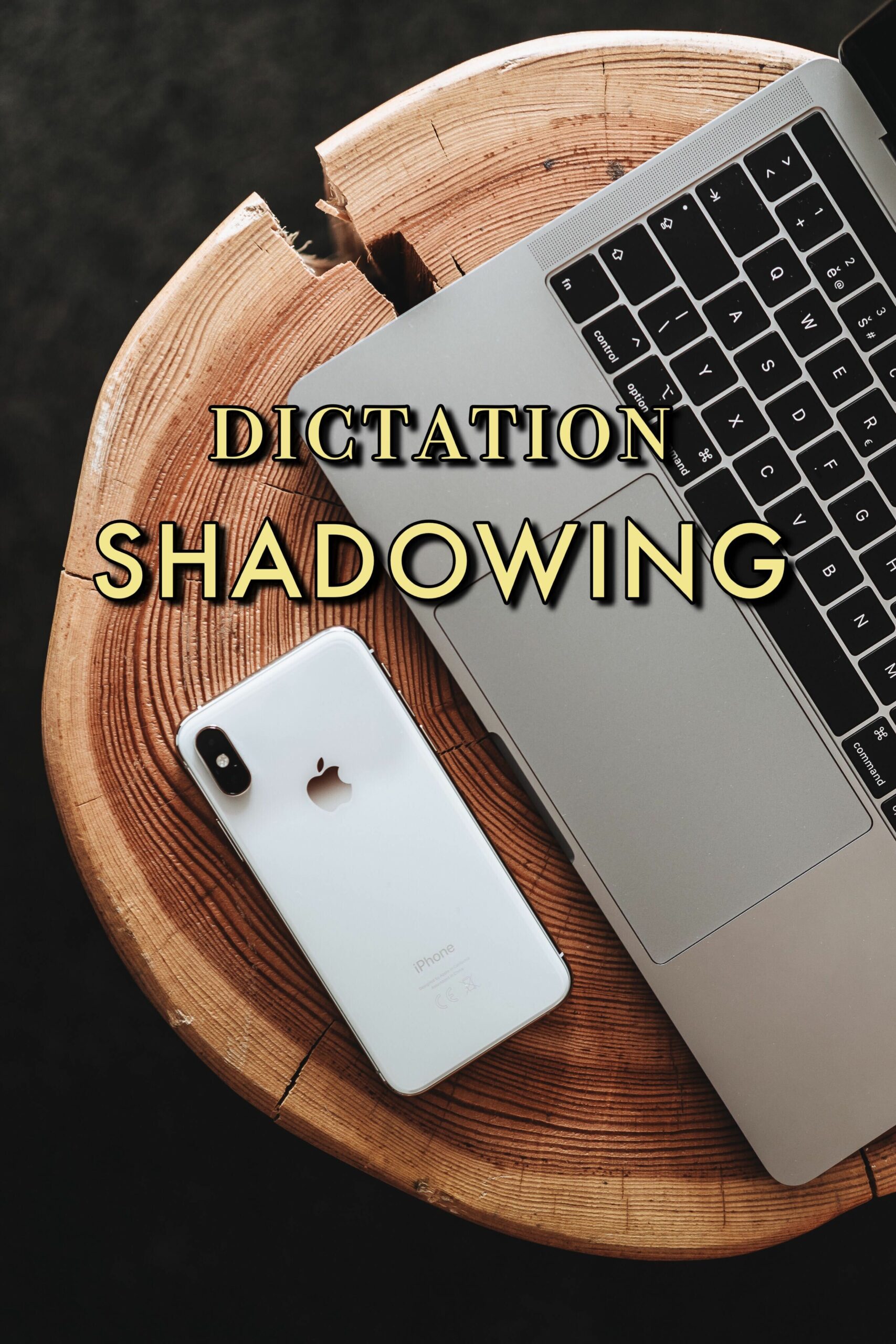
皆さんは外国語を学ぶ時、話すのが恥ずかしい、ミスをするのが怖い、文法と発音の問題で笑われるのが嫌い、などと思うことがありますか。言語学習の初期段階ではこのように思うことがよくあると思いますが、この段階での、「通じればOK」という考えは学習者に勇気が与えられるので、有効であると言えます。しかしながら、段々レベルアップしていくと、例えば、日本語歴6年半の私にとっては、通じるだけでは不十分で、できる限りネイティブに近づけるように努力していきたいと考えるようになりました。
ご存じの通り、ネイティブに近づけるには、「リスニング能力」と「スピーキング能力」が必要です。ここで、リスニング練習とスピーキング練習に効果的なディクテーションとシャドーイングを組み合わせた効率的な言語学習法を皆さんにシェアしたいと思います。
ディクテーションとシャドーイングとは?
ディクテーションとは、読み上げられる音声を書き取ることです。
シャドーイングについて、玉井(1997)の定義を引用します。シャドーイングとは、「聞こえてくるスピーチに対してほぼ同時にあるいは一定の間をおいてそのスピーチと同じ発話を口頭で再生する行為、又は聴解訓練法です」(玉井1997)。シャドーイングは本来同時通訳養成の訓練で使われている基礎訓練法の一つですが、「聴く」と「喋る」が同時に鍛えられる語学勉強法としてもよく知られています。
リスニングの強化、スピーキングの強化、語彙力強化
次は、このディクテーションとシャドーイングを組み合わせた学習法の具体的な効果、リスニングの強化、スピーキングの強化、語彙力強化をご紹介します。
繰り返し聴く、繰り返し喋る、また聴きながら喋るという作業も何度も繰り返されるので、自分の耳、口、舌が徐々に慣れてきます。このように、口の開き方や舌の位置を実際に発音したときの感覚で・理解・記憶するようになります。
語彙力の強化ですが、シャドーイングすることによって、個々の単語レベルではなく、フレーズ、文レベルの表現が記憶に残ります。例えば、「大学進学を希望するまで意欲を取り戻したAが学習習慣を身につけていく土台となったのが、生活習慣の確立です。」という文ですが、意欲、取り戻す、習慣、身につける、土台という個々の単語ではなくて、意欲を取り戻す、習慣を身につける、土台となったのは…ですのような使い方をひとまりで身につけることができます。
ディクテーション・シャドーイングの手順
私はシャドーイングにディクテーションを合わせた方法を使っています。ではこの学習法の具体的な手順をご紹介します。
1. 動画選定(ニュース、ドキュメンタリー、ドラマ、アニメ、バラエティー番組など、モチベーションをアップできるような動画ならなんでも良い)
2. ディクテーションする。(オリジナルの再生速度での音声を聞きながらディクテーションする。このステップにはある程度時間がかかります。慣れてきたら、動画内の全部の内容ではなく、自分がうまく使えない表現だけをディクテーションするのがより効率的!)
3. メモを取る。(聞き取りにくい部分、気になるところを箇条書きにする。表現の意味がわからないままシャドーイングするのはNG)
4. 本番 ▶ シャドーイング。(モデルのイントネーション、アクセントを意識しながら、シャドーイングする。*録音することが大事。第三者の立場で、自分の声を客観的に聴くことを通して、自分の長所と短所がすぐわかり、より良い発音へと向上させることができる。)
・一段階:テキストを見ながら繰り返しシャドーイングする。
・二段階:テキストを見ずに繰り返しシャドーイングする。
言語学習というのは長い長い道のりで終点がありません。ただ、毎日、毎週積み重ねていくとすごいことになります。ぜひ自分の目標言語を対象にして、実践して、一緒に言語能力を上げていきましょう!
参考文献:
玉井健(1997)「シャドーイングの効果と聴解プロセスにおける位置づけ」.『時事英語学研究』(105-116)
(蘇暁笛)