
TAさんによる言語学習についてのコラムの第8弾を追加しました。言語文化研究科D1の岡田茉弓さんによる、現地に溶け込んで言語を取り入れる ―バリの田舎での言語体験②-です。

TAさんによる言語学習についてのコラムの第8弾を追加しました。言語文化研究科D1の岡田茉弓さんによる、現地に溶け込んで言語を取り入れる ―バリの田舎での言語体験②-です。

前回のコラムにて、インドネシア語もバリ語もわからない状況に置かれた私は、辞書を片手に黙したと書いた。その理由だが、大きく分けて2つあった。1つ目は単純に話すことができないということと、2つ目は周囲の言葉を聞くことに徹していたからだ。この作業をする際に、私はバリ語とインドネシア語という2つの言語のどちらを優先して習得するかを決めなければいけなかった。
そこで私は、基本的にはインドネシア語を優先的に習得するようにした。なぜなら私に対して多くのインドネシア人はインドネシア語で話しかけ、多少わからなくても辞書等で参照できたためである。また、単純に文法や語彙がバリ語と比べて簡単だったので習得が容易だと判断したためである。
例えばインドネシア語で「enak(エナック)」という言葉がある。辞書通りの意味合いなら、「おいしい」なのだが、日常的には「いいね!」という意味合いで食事以外にも頻繁に使用する。靴や服のセンスを褒める時、状況が自分にとって好都合なものに関しても「enak」という言葉を使用する。そして、現地のひとびとが私の物を指さし、「enak」というのをどのように口調で使っているのかもジッと見て聞いていた。もちろんこの言葉はポジティブな意味合いが強いので、和気あいあいとした場面で、明らかに私をおだてるように使用する。そして最後に、その様子も込みで、「enak」という言葉をこちらから使用してみて、自分の使い方がおかしくないかを確認する。
もちろん、これは「enak」に限ったことだけではなく、同時並行で膨大な数の単語やコロケーションを覚えていった。朝食の場面や会議の場面等で過去に現地の人々が使用していた言葉をそっくりそのまま述べていくのである。つまり、過去に遭遇した同一場面のインドネシア人と同じようにふるまうことを意識したのである。もちろん、その意味はある程度は辞書で調べることができるが、どのようなまとまりで話すべきなのかは過去の記憶に沿って話している。相手の反応が特に悪くなければ、そのまま深く調べず新たな場面での言語習得に努めていった。このようなざっくりしたやり方なので、どこまでがインドネシア語の表現で、どこからがバリ語独特の表現であったのかはいまだに整理ができていない。
また、儀礼に参加する際によく聞くバリ・ヒンドゥーの儀礼にかかわる言葉に関しては、そういうものかという認識でとどめ、厳密に日本語で対訳を求めることをやめた。例えば、「tilem (新月)」という言葉がある。この言葉は暦の上での新月の日を表すものでもあるが、tilemに関わる式典や、その準備に関わることも指す。とにかく意味が「新月」という概念よりも広いのである。その際に、どこまでの行為が「tilem」の概念に入るのか、入らないのかまでは追及しなかった。
このような方法でインドネシア語とバリ語を習得した私だが、この方法だからこその失敗談もある。
バリ語での失敗エピソードなのだが、ある日、ある教員の真似をしてバリ語で「ご飯を食べる」という言葉を話してみたが、どうも周囲の教員の反応がおかしい。何か間違ったかしらと思っていたのだが、言葉自体は間違っていなかった。しかし、「私が」使うのが間違っていたのであった。
私はバリでkadek mayumiと呼ばれていて、kadekは次女という意味だが、ただ次女であるだけでなく、平民の次女であることを指す。だから私は平民の使うバリ語を話さなくてはいけないのだが、件の教員が発した「ご飯を食べるは」王族階級の表現だったのだ。つまりその教員は王族階級であったのだ。私が誤って王族階級の言葉を使用したのは、他意はないと周囲の教員は理解してくれていたが、今後使用を続ければ私にとって不利益となると考えたバリ語の教員が、なぜ私が使用すると誤りなのかを、易しいインドネシア語で丁寧に説明をしてくれた。その時、安易に言語を真似たことを反省するとともに、kadekとして周囲の人々が認識し、私がバリの文化の中に溶け込めるように手助けしてくれることが嬉しかった。この時だけではなく、赴任期間中、公的な場面では教員たちが、プライベート場面では大家夫妻が、私が誤った使用をした際には、どういう意味なのか、どういう言葉が正解なのかを教えてくれた。
様々な失敗は何度か犯したものの、周囲の助けを得ながら私はインドネシア語と若干のバリ語の言語獲得を赴任期間中順調に進め、最終的には業務連絡程度であれば難なく応答できるようになった。言語を習得すること自体も楽しかったが、言語を習得する中で周囲の人たちとの絆が深まりを感じるのも、現地で言葉を獲得する際の醍醐味だった。
(岡田茉弓)

TAさんによる言語学習についてのコラムの第7弾を追加しました。言語文化研究科D1の岡田茉弓さんによる、現地に溶け込んで言語を取り入れる ―バリの田舎での言語体験①-です。

このコラムを読んでいる皆様の中に、海外に行き、現地のひとびとが何を言っているのかさっぱりわからないという体験をした方は多くいると思う。しかし、その何を言っているかさっぱりわからないという環境の下で、一人で一定期間暮らさなければいけないという方はなかなかいないかもしれない。筆者はそのような体験をした一人である。もしかすると、このコラムを読んでいる方の中に将来的にそのような体験をする人もいるかもしれない。そのために、どのように言語を私が獲得していったのかをこのコラムで語っていきたい。
私は国際交流基金の「日本語パートナーズプログラム」でバリ島に派遣され、現地日本語教師のALTとして半年間滞在したことがある。派遣期間は半年である。私はバリと聞いて青い海、白い砂浜のバカンスを想像していた。しかし、バカンスとして観光開発されたのはバリ州南部の一部地域で、ほかの多くの地域は現地の方が細々と暮らす地域である。私が派遣されたのは、バリ州東部のクルンクン郡である。クルンクン郡は、オランダ統治前の古き良きバリの伝統が色濃く残る地域である。
インドネシアはインドネシア語を国語としており、官公庁の文書やテレビや新聞といったメディアではインドネシア語が使用されている。しかし一方で、多民族・多言語国家であり、各民族の言語は私的な領域を中心として広く使われている
派遣前にひと月の研修期間があり、その中で毎日3時間程度のインドネシア語の授業もあった。毎週土曜にはテストがあり、なかなか厳しい研修で、これによって挨拶や基本的な名詞や動詞は覚えて現地に臨んだ。
しかしながら、ひと月の研修を経て派遣された時、私のインドネシア語の能力は、自分の意思を最低限伝えられる程度であった。最低限というのはどのくらいかというと、「ご飯を食べる」「私は寝る」といったぐらいのもので、大人として最低限のレベルどころか、幼児レベルであったということは察していただけるだろう。そのうえで、現地で私は想定外の事態に出会う。なんと、私が派遣されたバリ州クルンクン郡では、日常会話においてはバリ語の使用がより優勢だったのである。バリ語はバリ・ヒンドゥー教と密接に関連があり、自分の身分に応じた表現とともに相手の身分に応じた敬語の表現がある。そのうえ、文法もインドネシア語に比べ複雑である。また、表記にはインドネシア語のようなローマ字ではなく独自の文字が使われているため、初学者には理解が難しい。
国語であるインドネシア語は官公庁の文書や出版などのメディアのような公的な領域で使用される一方で、プライベートな場ではバリ語が話されるのが普通である。もちろん、私自身は見た目から外国人だとわかるので、バリ語で話しかけられることはない。しかし、市場や学校の事務室、学生たちの会話の多くはバリ語がメインであった。ホームステイ先の大家夫妻はインドネシア語にバリ語なまりが入ることもあり、聞き取りが困難に感じた。
周りのみんなは私に話しかけてくれる時にはバリ語からインドネシア語にコードスイッチしてはくれたが、業務連絡を聞く際瞬時に行動できないという場面が何度かあった。例えば、学校の教頭先生が全体に明日の急な予定変更を伝える。周りは同意してその場が収まるのだが、私だけが置いてけぼりになってしまう。もちろん、それぐらい重要な情報なら周りの人に聞けばだいたい教えてくれるが、プライベートな会話ではそうはいかない。周囲がどっと盛り上がるのに、自分だけわからずあいまいに笑っておくしかないのである。頼みの綱のインドネシア語も怪しい状況のため、積極的に質問もできなかった。また、バリ語の中の、伝統的なお祭りに関する語彙の多くは、バリの人々のインドネシア語の中でもそのまま使用されている。そのため、文法はインドネシア語で話していても、語彙の多くはバリ語のため意味が取れないという場面が何度かあった。
私は英語が通じると思っていたが、英語を習得している人々の多くは南の観光業に携わっている人々で、私が派遣された地域では多くの人は話すことができなかった。学校に行けば現地の日本語教師がいたため、なんとか業務はできたが、ホームステイ先では、英語も日本語も通じず、なけなしのインドネシア語で大家さんと意思疎通をはからなければならない。
そのような状況下で私は言語習得のために何をしたのか。それは1か月近く「黙した」のである。最近では珍しく紙の辞書を片手にだ。
どうして私がそのような珍妙な行動に出たかは、次回のコラムで書いていきたい。
(岡田茉弓)

TAさんによる言語学習についてのコラムの第6弾を追加しました。言語文化研究科D2の張碩さんによる、楽しく効果が得られる英語学習チャンネルです。

今、市販の教材を使わず、英会話教室に通わなくても、インターネット上にある沢山のコンテンツで言語学習をすることができる。その中で、YouTubeはほぼ無料で、どこでもいつでも利用できるというメリットがあるため、私はリスニングを練習する際に、YouTubeのチャンネルをよく使う。
YouTubeでは色々な英会話レッスンの動画が載せられているが、「Daily Dictation」が一番おすすめのサイトである。今日はこのチャンネルについてご紹介する。(「Daily Dictation」には有料版の「Daily Dictation Members [DDM]もあり、ビデオの中で加入の誘いもされているが、ここで紹介する無料版だけでも十分な学習効果がある。有料版の利用は各自の判断で。)
1.「Daily Dictation」は何であるか?
名前の通り、Daily Dictationはディクテーションを行うチャンネルであるが。外国語学習に効果的な「ディクテーション」の方法をご存じだろうか?「ディクテーション」もともとは書き取りの意味であるが、外国語学習につきリスニング力を鍛えるために読み上げられる外国語を書き取ることである。「ディクテーション」を行う際に、聞いた一語一語を書き取るために集中することで、リスニング力を上げるのに非常に効果がある。
Daily Dictationは、リスニングとリスニングの理解力を向上させたいESL(English as a second language、第二言語としての英語、またその話者)を対象としているチャンネルである。チャンネルの所有者は韓国に在住している40代のアメリカ人男性―Shaneである。Daily Dictationにおける動画の長さはほとんど10分~25分で、動画の公開コメント欄を見れば、世界各国の学習者から非常に良い評価を受けていると見られる。
2.「Daily Dictation」の内容
まず、ひとつの課題について、音声が4回流れる出題編と答え合わせと解説を行う解答編の2部に分かれている。解答編では、Shaneは音声のテキストを黒板に書き、そのテキストの内容について、詳細に説明してくれる。具体的に、ある単語の意味は何であるか、日常生活でどのように使うか、特定の単語と連結したら、発音がどのように変わるか(リンキング)をしっかり教えてくれる。その後、Shaneはテキストの内容について、自分の意見と考えを視聴者と共有していく。例えば、あるリスニングはアフリカの子どもの貧困に関わる内容であるから、Shaneはアフリカの子どもを救うため自分は何ができるかを考え、生活資源の無駄使いを反省した後、視聴者たちにアイデアや意見を求めたということがあった。動画の内容をよく理解したあと、Shaneと一緒に音声を聞き、シャドーイングして、音声の内容を復習する。
このようにして、新たな音声について、新しいディクテーションのトレーニングを以上のプロセスでやり続けていく。
3.「Daily Dictation」の特徴
一言でいえば、「Daily Dictation」の特徴とは、気軽に本場の英語が学べることである。毎日平均20分を利用しさえすれば、リスニング能力を向上させられると同時に、様々な知識が得られる。
また、Shaneはコメントの投稿を受け付けている。もし前日のリスニングの内容について、さらに議論したいことを、彼に投稿したら、あなたの質問あるいは意見が次回のレッスンで議論される可能性がある。
Daily Dictationの教材には英語レベルの表示がないが、教材により難易度はさまざまである。例えばトークショーの英語はかなりレベルが高く、反対に子供向けのアニメは若干簡単すぎることがある。ただし、たとえリスニングの内容を全く聞き取れなくても、その後のShaneの解説を聞いて、新しい知識を学ぶことができると思うから、時間の無駄とは言えないのではないだろうか。私は現段階で、負担に感じることなく、「Daily Dictation」の122Daysまで学んだ。いつの間にか、英会話を聞くとき、アメリカドラマを見るとき、会話について理解できる内容が増えてきたと感じている。
リスニング能力を向上させたい方々もぜひ「Daily Dictation」使ってみてください!
↓
URL: https://www.youtube.com/user/dailydictation
(張碩)

我就读的高中除了英语之外还能选修第2外语。当时由于父亲从事对日贸易相关的工作,所以我也受其影响选了日语,在学校除了英语学习之外还会每周上一次日语课。由于日语课程和升学没有太大关系,所以课堂氛围和其他科目的教师主导的课堂不同。日语课上,老师经常经常会邀请日本外教与我们进行交流,或者组织我们排练文化节的话剧,氛围相对轻松。因此,即使我的日语成绩常年稳定在倒数第二位,在高中开设的所有课程中我仍然最喜欢日语,也喜欢说日语的自己。在学校经常用“半桶水”的日语和外教有一句没一句的搭话,周末时就在家看看日剧,模仿屏幕里人物的说话方式,无意识间开展着日语实践。尽管成绩很差,当时的我却对日语学习充满了信心,这样的心情现在我仍然觉得十分不可思议。
<享受日语学习的“修炼”>
我原来就喜欢英语,开始接触日语之后,对日语也开始抱有兴趣。因此在高二得知能有机会保送进入大学外语专业的时候,便下定决心想要一试,进入日语系对我来说也是一个不错的选择。当时在日语班上,有个朋友向我提议,好不容易学了一年,要不考个N2试试吧。于是在高中学习之余,考取日语资格,变成为了我的一大目标。从这时开始,高中的学业负担也开始逐步加重,我的日语学习就像见缝插针一样地进行着。当时我曾经持续半年,每天早晨早起1小时,在6:30到7:30的这段时间里在没有人的教学楼屋顶一个人学习日语。这段经历至今让我至今印象深刻。周末在家放松追剧的时候,我会一遍看剧一边写台词,后来竟把日剧“Cold Blue”一整部完整的台词都写到了笔记本上。现在回想起来,我甚至觉得有些不可思议懒散的自己竟然也能这么刻苦,但是高中的我却完全没有感觉到一丝疲惫。也就是从这个时期开始,我的日语突然开始突飞猛进。
<从日语学习到走向更广阔的世界>
进入高3前的那个暑假,我考过了N2,高中十几个科目的学习和日语学习都有条不紊地进行着,成绩也都还可以。因此我对于高中整体学习的热情和自我效能感也提高了。进入高3之后,我在保送考试中顺利考上了第一志愿的外国语大学,离开了家乡,进入了北京某大学的日语专业。之后也发生了许许多多关于语言学习的故事,但是让我强烈感受到语言学习和自己密不可分的,还是这段高中语言学习的经验。
<日语对我而言 >
对高中时期的我来说,日语学习当中几乎不存在由于考试压力而需要和他人进行横向比较的因素,取而代之的是在外教家里的圣诞派对、文化节的话剧演出、没有人的教学楼屋顶的朝阳等等充满喜悦、快乐和希望的经验。或许这正是我想要继续日语学习的原因。
我喜欢日语,并且甘愿在繁忙的高中学习里花费大量时间学习日语的原因,可能在于在填鸭式的被动学习为主的高中阶段,只有日语学习是我给自己设定的目标,是基于我个人意愿的决定。通过语言学习,习惯于被动学习的我第一次萌发了关于“自我”的意识,有了想要实现的目标,并且愿意在学校教育带来的种种约束的范围内为自己的目标而努力。对我来说,语言学习的经验带赋予了我远远超过语言学习本身的力量,至今仍然对我的学习和研究生活产生深远的影响。
(陳静怡)

TAさんによる言語学習についてのコラムの第5弾を追加しました。言語文化研究科D1の陳静怡さんによる「受験勉強の合間にほっと一息、わたしにとっての言語学習の喜びと楽しみ」の中国語版「应试学习中的短暂喘息,语言学习带给我的喜悦和快乐」です。
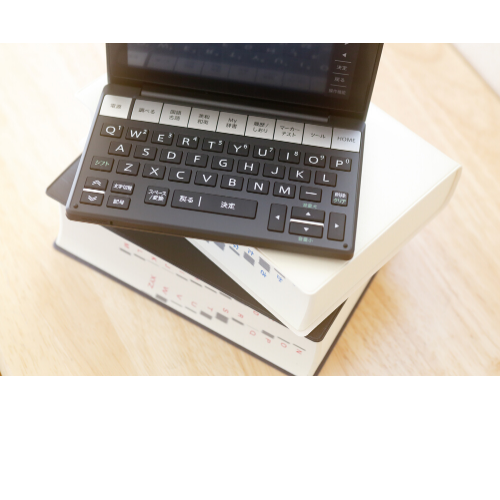
わたしにとって、言語学習は受験勉強の重圧が伴う学習と違い、バタバタしている日々の中に常に喜びと楽しみを与えてくれるものでした。このように感じているのは、高校での言語学習、特に日本語学習と深く関わっています。ここではわたしと日本語の出会いから、推薦入試で大学の日本語科に入るまでの経験を記述します。読者のみなさんが自らの経験と照り合わせ、自分にとっての言語学習は何かを深く考えることを通して、頑張れる力がみなぎることを祈ります。
<日本語との出会い>
わたしが通っていた高校では英語とは別に第2外国語が選べました。父が当時日中貿易の仕事をしていたこともあり、わたしは日本語を選び、英語とは別に日本語の授業を週1回受けるようになりました。日本語の授業は受験と関係ないため、先生が一方的に教え込む教科学習と異なり、日本語ネイティブの先生を招いたり、文化祭の日本語劇を準備したりすることが多く、常に自由とリラックスの雰囲気のもとで開講されていました。このため、日本語の成績がクラスの後ろから2番目でさまよっていたにも関わらず、高校の授業の中で、わたしは日本語の授業が最も好きで、日本語を喋る自分のことも好きでした。学校ではよくネイティブの日本語の先生と通じない日本語で喋ったり、週末には日本語のドラマを見て話し方を真似たりして、日本語実践を無意識の間でしていました。そして、不思議なことに日本語はきっとよくできるようになるという自信も抱えていました。
<日本語学習の「修行」を楽しむ>
英語はもともと好きで、日本語も好きになったため、高校2年の頃、わたしは推薦入試で大学に入ることを考えていました。特に、日本語学科も悪くはないと思いました。当時第2外国語の日本語クラスでは、せっかく1年くらい学習してきたのだから高校卒業までに日本語能力試験のN2の資格が欲しいという友達がいたので、わたしもN2を目指していました。ほかの教科学習も徐々に忙しくなったため、日本語学習は隙間を縫う感じで行っていました。早起きして6時30分から7時30分まで1時間、誰もいない高校の屋上でN2の試験勉強を半年くらい続けたことは今でも印象深いです。週末にドラマを楽しむ時も、見ながらセリフを書くようになり、気づいたら、なんと「コード・ブルー」のセリフは全部ノートに書いていました。今振り返ってみると、相当大変なことでしたが、当時は全然疲れを感じていませんでした。この頃から、急に周りの人が信じられないほど日本語が上手になりました。
<日本語学習から広がる世界>
高3に入る直前の夏休みに私はN2に受かり、高校の十数科目と日本語学習、両方のバランスがよく保たれていたと感じたため、学習全体に対するモチベーションや自己効力感も上がりました。高3に入った後、私は推薦入試で無事に第一志望の外大に受かり、故郷の地方都市から離れ、北京にある大学の日本語科に入りました。その後も言語学習に関するいろいろなエピソードがありましたが、わたしが自らと言語学習との関わりを強く感じたのはこの高校時代の経験でした。
<わたしにとっての日本語学習>
高校時代のわたしにとって、日本語学習は、受験競争のように他者との横断的な比較という要素が少なく、その代わりに、ネイティブ教師のマンションでのホームパーティー、文化祭の日本語劇、学校の屋上の朝日の中での学習といった経験に満ちており、いつも喜びと楽しみ、そして希望に満ちていたため、頑張りたいと思ったのかもしれません。
わたしの日本語が好きになった理由、忙しい受験勉強の日々を過ごしながらも日本語学習に時間を費やした理由はおそらく、押し付けられた学習が中心だった高校時代、日本語学習だけがわたしの自ら見つかった目標で、自分の意思で決めたことだったからと思います。言語学習を通して、受動的な学習をしてきたわたしは初めて「自己」に関する意識に気づき、自分が叶えたい目標を持ち、学校教育の枠組みの中で自らの目標のために頑張ることができました。このように、わたしにとって、言語学習の経験は言語そのものの学びを超えた力を与えてくれているものであり、今でもわたしの学習と研究全般に影響をもたらしています。
(陳静怡)
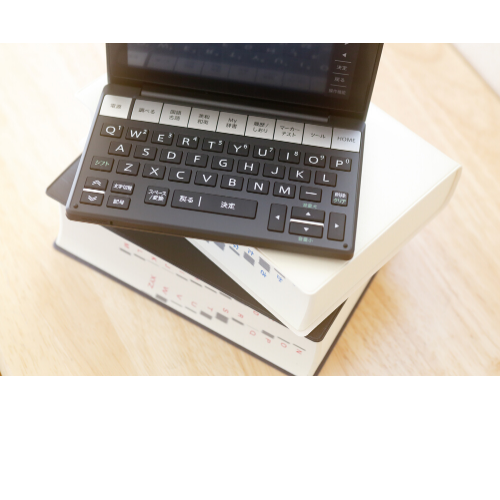
TAさんによる言語学習についてのコラムの第4弾を追加しました。言語文化研究科D1の陳静怡さんによる「受験勉強の合間にほっと一息、わたしにとっての言語学習の喜びと楽しみ」です。