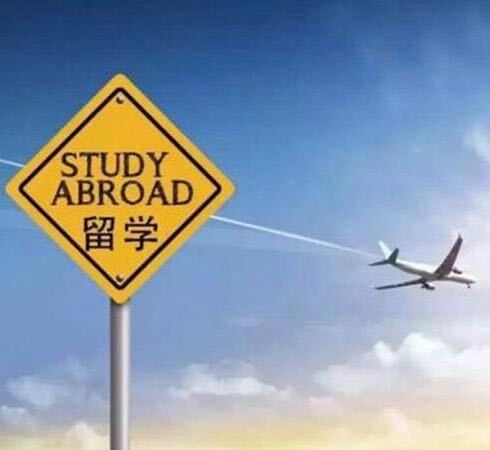日本語 (留学生対象)・英語・韓国語・中国語の会話練習を実施しています。
パートナーと1対1で、ご自分が用意した話題について、会話の練習をしてみませんか?
1セッションは20分間です。
プラザでの対面での練習でも、Zoomでの練習でも、ご希望によりどちらでも対応します!
会話練習は興味があるけれど、話題をどうやって見つけるかわからないひとには、会話トピックのヒントとなる資料を用意しています。
秋冬学期は以下の日程で開催します。
日本語: 水曜 12:00-13:30 (12:00~12:20, 12:30-12:50, 13:00-13:20 に2人のパートナーが対応します。計6セッション) 予約締切: 毎週月曜17時
英語: 月曜 12:00-13:30 (12:00~12:20, 12:30-12:50, 13:00-13:20 計3セッション) 予約締切: 毎週土曜17時
水曜 12:00-13:30 (12:00~12:20, 12:30-12:50, 13:00-13:20 計3セッション) 予約締切: 毎週月曜17時
中国語: 月曜 12:00-13:30 (12:00~12:20, 12:30-12:50, 13:00-13:20 計3セッション) 予約締切: 毎週土曜17時
韓国語: 月曜 10:30-12:00 (10:30-10:50, 11:00-11:20, 11:30-11:50 計3セッション) 予約毎週日曜17時
申込はそれぞれの締め切りまでに、メールにて (plaza[at]lang.osaka-u.ac.jp)
時間を調整したうえで予約できたセッションについて返信しますので、それを以て予約完了とします。
なお、予約したセッションの日時に都合が悪くなりキャンセルしたい場合にはなるべく早くお知らせください。
当日無断キャンセルされた場合はそれ以降のご利用をお断りしますのでご了承ください。
ご参加、お待ちしております!




 大阪大学の学生・教職員で、日本語を学んでいる人向けのイベントです。
大阪大学の学生・教職員で、日本語を学んでいる人向けのイベントです。