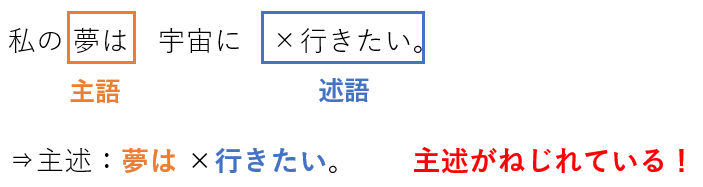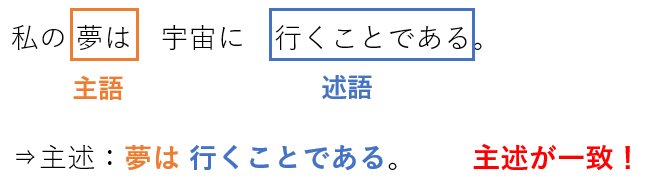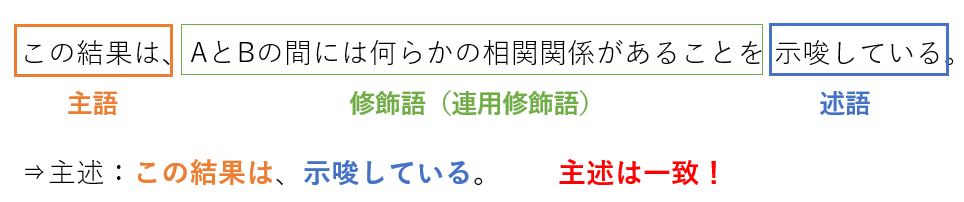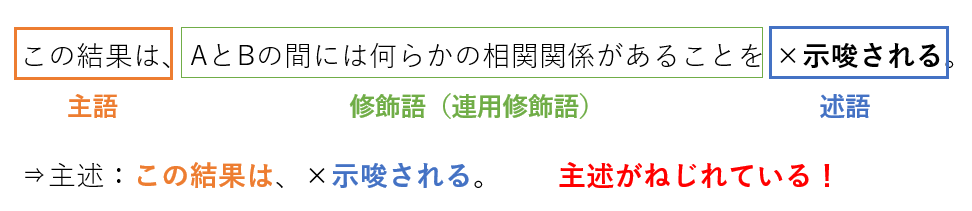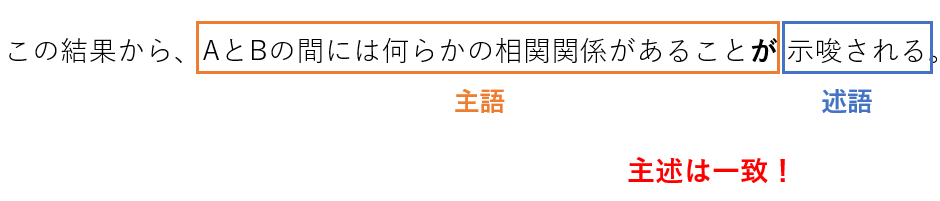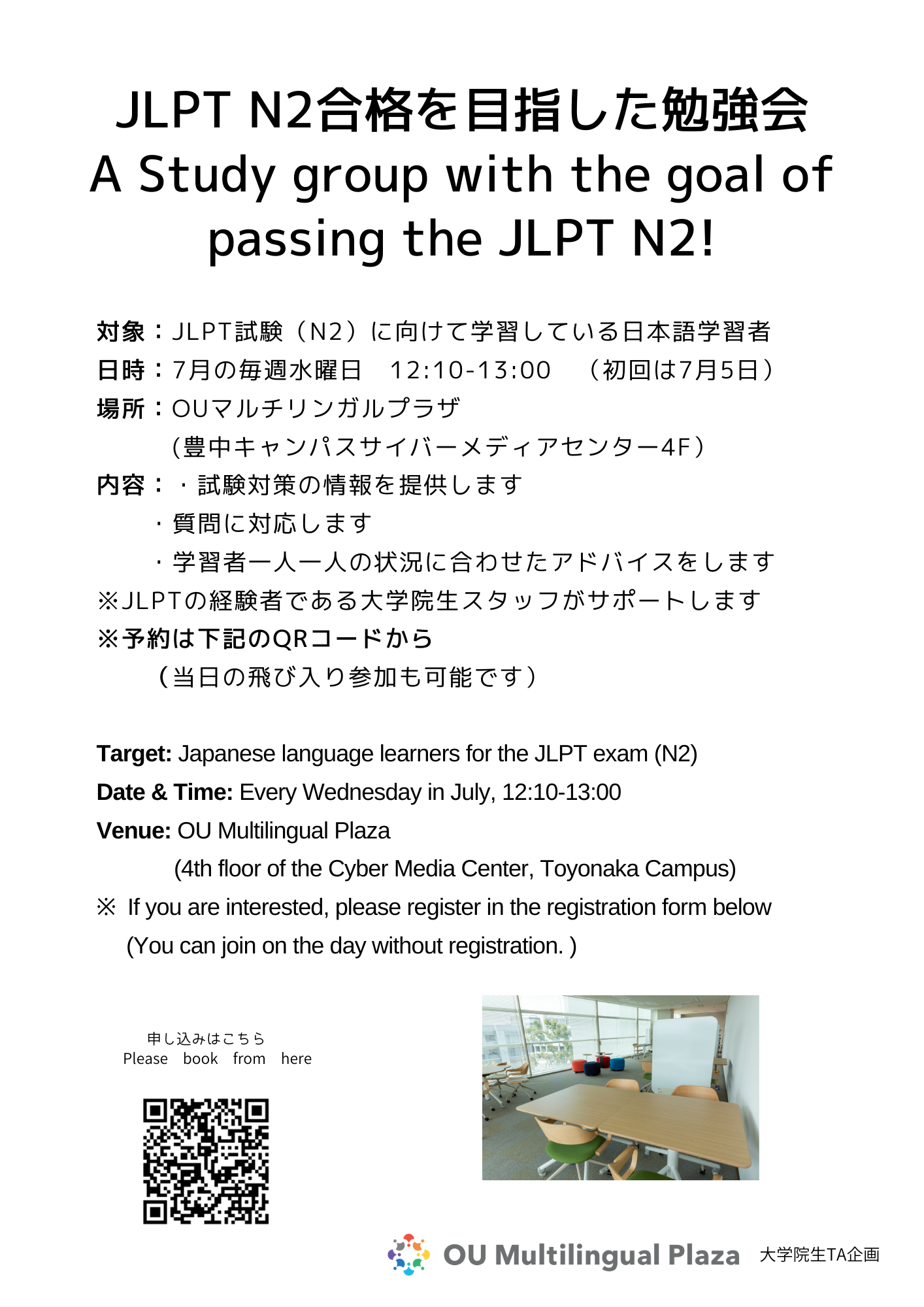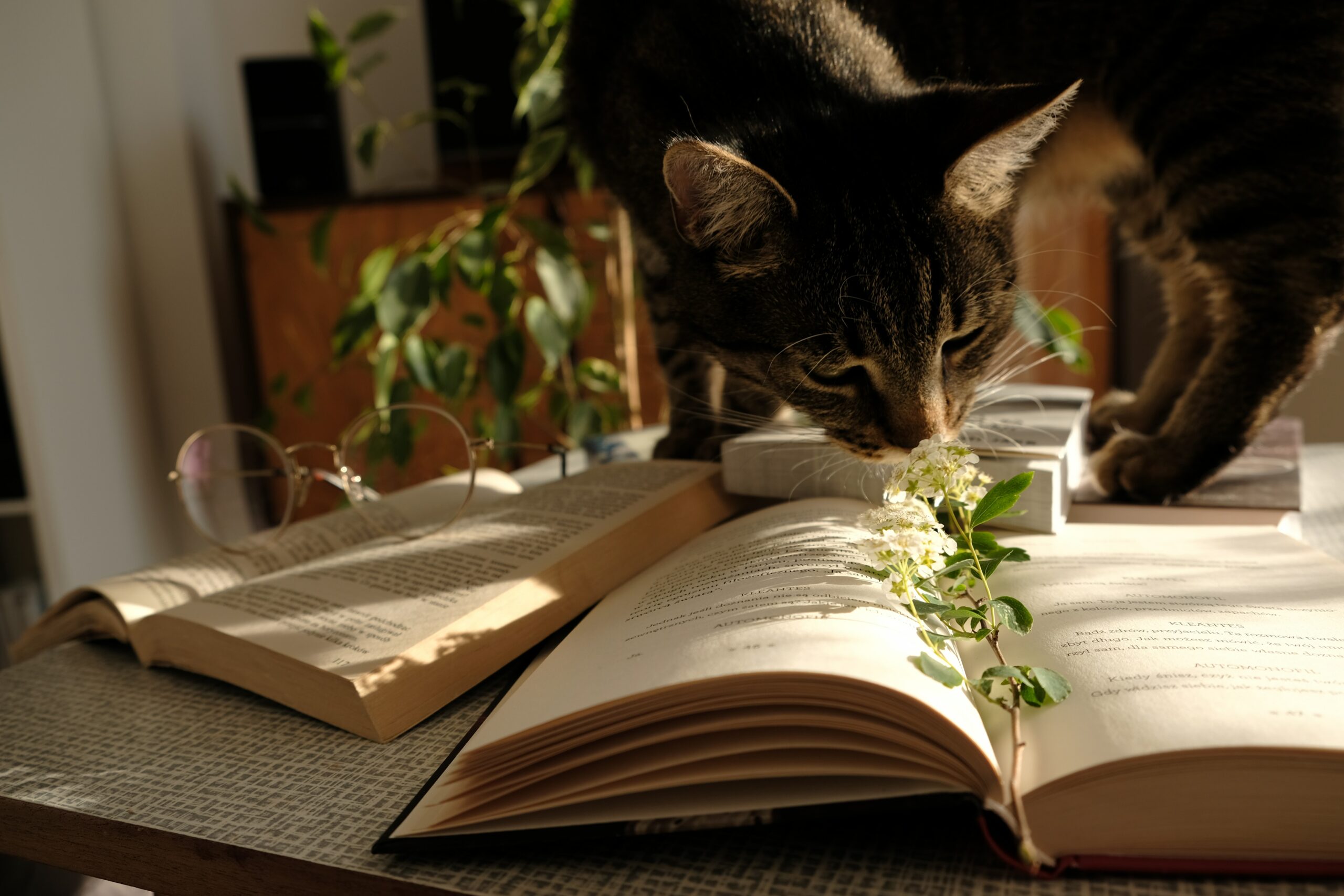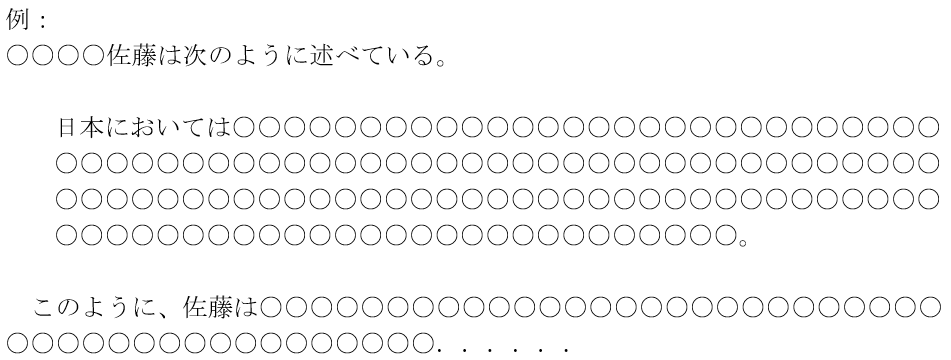こんにちは。特任研究員の孫聴雨です。今回は好きな日本のドラマの話をします。
日本のドラマが好きです。これは特に日本語学習の経験と関係なく、日本語を勉強する前から好きでした。なぜかというと、日本ドラマのキャラづくりにはすごく惹かれるからです。一番好きなドラマは『過保護のカホコ※1』です。このドラマの主人公、カホコはいわゆる箱入り娘で、生活における意思決定をすべて母親にゆだねる22歳の女子大学生です。ドラマの初め、私はまったく主人公の魅力を感じることができませんでした。何ひとつ頑張らないし、自分の意志を持たない人のどこが可愛いのかと理解不能でした。でも、物語が進むと、カホコははじめ君という学生と出会い、はじめ君への恋愛感情を通して、だんだん変わりました。いつの間にか私は応援したくなっていました。ここで日本のドラマの一つの特徴に気づきました。それは平凡な主人公の人物像を細かく作り込んで、成長させ、共感を求める点でです。共感が求められる主人公は情けない主人公だけではなく、犯罪を犯す主人公や、道徳的規範から外れている主人公もいます。
『黒革の手帖※2』の原口元子は銀行員の地位を利用して、大金を横領した後、銀座のクラブのママとなりました。ドラマの題材に「犯罪」というテーマを選んだが、最後に裁くわけでもなく、そのまま成功させました。私から見ると、むりやりに「罰を与える」という正しい結末をつけるのではなく、そのまま成功させる物語が興味深いです。人が野望を持ち、それを成し遂げるということの魅力を感じました。
『昼顔※3』というドラマの名称の意味は夫がいない平日昼間に不倫をする主婦のことをさしているそうです。主人公の笹本紗和はもともとごく平凡な主婦ですが、高校教師の北野との出会いによって、少し変わりました。自分の中でもがいた結果、やがて越えてはいけない一線を越えてしまいました。「不倫」をテーマにする作品が日本で特に多い感じがして、不倫というテーマをドラマの題材にして、これほど多くの人が受け入れることにびっくりしました。でも確かに私も日本の不倫を題材とするドラマをみて、道徳的に許されない恋愛なのに、普通の恋愛のような純粋さが感じられます。
このような他人からの共感を得られなさそうな主人公と出会う時、私が抱いた最初の感想は「なぜこのような人でも主人公になれたの」でした。物語を作る時、平凡な人はいいですが、悪役まで主人公にするのが私から見るとすごく新鮮でした。しかし、物語が進むと共に、犯罪者や不倫者といってもやはりみんなと同じで普通の人でもあることがわかりました。だんだん主人公と共感できるようになって、いつの間にか納得ができました。
これは価値観の話につながると思います。今までの教育でなんとなく「正しい」ものだけを追求することを期待されてきたため、このような独特の主人公を見ると、間違っているとつい思っています。しかし、実際いろいろなことを経験してみると、人の両面性が見えてきました。人というのは自分と自分の人生を完全にコントロールできる生き物ではなく、みんながみんな順風満帆の人生が歩めるわけではありません。窮地に陥った時にはあがいたり、自分のために何かをやってしまったりすることも現実には起きうるのではないでしょうか。
誰でも少しぐらいあがいたことがあり、共感を生み、このような作品がヒットしたのかなと思います。このような主人公から自分や価値観についていろいろ考えさせられてとてもいい経験になりました。完璧ではない主人公の物語を楽しんでみてはいかがでしょうか。
※1『過保護なカホコ』は2017年に日本テレビ系で放送されたドラマ。
※2『黒革の手帖※』は松本清張の長編小説、何度もドラマ化にされた作品。
※3『昼顔※』は2014年にフジテレビ系で放送されたドラマ。
孫聴雨